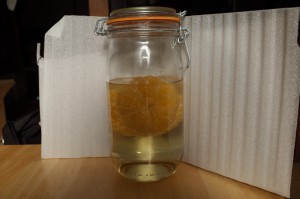いやー、面白かった!
さて、アトルニアを現在の姿たらしめている「革命」の真実に、アトルニアから遠く離れたクレッサールの砂漠にて迫るDXたち。前巻までで王国の崩壊を企むクエンティンの策略にはまり、見事に分断されてしまったDXたちでしたが、本巻では仲間が集い、ついに全面対決と相成ります。奴隷商に売られたDXを助けに来たライナスとルーディー、そして「サンダーレンのマダム(9巻以来実に16巻ぶりの登場)」や奴隷商カリファの力すら借りて、父リゲインと同じくユージェニと刃を交えます。さて戦いの行方は、というところで次巻に続きます。
もう何年連載しているのか分かりませんが、主人公DXの着実な成長を感じます。なんというか、必要に応じて人に任せたり、他人の力を借りたりすることに躊躇がなくなってるんですよね。本作、主人公たちの個人のレベルとしては最初からかなり高いところにある作品ですので、パワーアップする余地というのがこういう、ジミーな対人スキルだったり、リーダーシップだったりするわけですが、パワーアップした能力が遺憾なく発揮されるという意味では意味ではロボットアニメにおける主人公機交代回くらいのカタルシスのある巻です。大変読んでいて気持ちが良い。
他方、結局かつてなにがあったのか、ということについて、色々と明らかにはなるんですが、結局最終的に本事件にどのようなオチがつくのかは見えません。現在のところの敵に当たるクエンティンにしても、彼の命を取れば全てが解決するというものでもないでしょうし、何を以て彼が敗北するのか、色々伏線は撒かれつつ、どこがどこにつながっているのかは読めません。おがきさんのストーリーテリングが光ります。あと、いろんな人の天恵(超能力のようなもの、最近だと精神干渉系の能力者が多数登場している)がいったいどういうものなのか、サッパリ分かりませんし、その辺も明らかになるのかなぁなんて。
先に書いたように、9巻以来16巻越しに登場しているキャラクターがいたり、何度も読み返して何回も楽しめるスルメのような王道ファンタジー。本レビューを見て気になった人がいたら、7巻位までかなぁ、とにかくまとめて読んでみて欲しいです。先に行けば行くほど、面白くなりますので。損はさせません。
今巻から限定版ではなく特装版となりましたが、おまけ漫画は主人公たちが身につけている武術について。前巻の最後に出てきたライナスの「裏打ち」の舞台裏が見えます。
さて、次は半年後、待ち遠しくて仕方がありません。
25巻の感想
24巻の感想