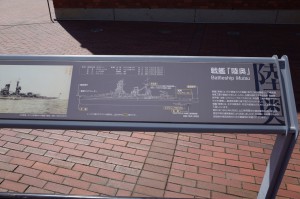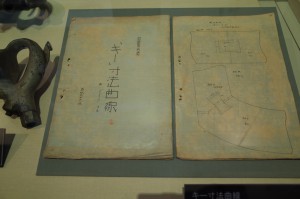本編の後日譚に属する短編を集めた短編集です。以前、星海社のネットラジオで読者から色々とリクエストが来ていたのを覚えていますが、それへのアンサーなんだなと読んでおりました。前巻Fと同様に各話毎に手短な感想を書きます。
##第1話 私のトリさん
主人公は子どもたちの1人、サキ(確か日本人とタイ人のハーフという設定だったはず)、彼女が東京の高校に通い始めた後の、ある日の出来事を描いたエピソード。彼女がどうやってアラタの元に来たのかもちょっとだけ語られ(スモーキーマウンテン出身という設定や病弱だったという設定がより具体的に語られる)、本作を通じてサキというキャラクターに厚みが出ます。本筋とは外れますが、日本や東京が異様に時間にうるさい、それを誇らしく思っているのがおかしい、というカルチャーギャップは結構面白いなぁと。日本人に限らず西洋人ですら、産業革命以前はそう言う感覚だったらしいですし、言われてみると確かにそうかもしれません。
##第2話 新しい首輪
シリーズの主人公アラタに関わった順で言うと、メインヒロインのジブリールより早いホリーさんの話。ジブリールとアラタを奪い合う女の戦いと、ただれているようで、まったく健全なアラタとホリーの会話劇が主題なのかな。表だってキャットファイトするわけではないので、冷戦みたいなもの、周囲が大変な思いをしているのが少し笑えます。明確に書かれているわけではないですが、仕事の話に集中して、周りのことが分からなくなっているアラタって本当にかっこいいんでしょうね。それこそ対局中の棋士みたいな感じで。
##第3話 若きイヌワシの悩み
アラタに最初からついてきていた子どもたちのうち、彼に比較的近い位置で物を見ているイブンの話。傭兵をやめた後にどうするのかという話で、多分第1話のサキの話の前日譚になるのだろうと思います。イスラム圏の人の職業観が垣間見えて面白いエピソードでした。職人に弟子入りしてオンザジョブで仕事を覚える江戸時代以前の日本に近い職業観なのかな?近代化されていない地域の出身だから、学校というものはイスラムの神学校しかない、ということみたいです。
##第4話 子供使いの失踪
アラタ一行が徳島で開催されているイベント「マチアソビ」に来て、その上で騒動に巻き込まれるという話。失踪という言葉の通り、アラタがいなくなって部隊が非常に混乱します。著者の芝村さんの、おそらくは知己の人々がキャラクターとして出てくるのと、氏の他の著作からキャラクターやメカが登場します。が、それらを僕は読んでいないので、胸が躍ると言うことはありませんでした。そう言う意味でもコアなファン向けのファンサービスみたいなものかと思います。
各エピソードの後に色々とさらに短いサブエピソードが挿入されて、その中にはなかなかドキッとする物もありました。それは読んでのお楽しみとしておきましょうか。