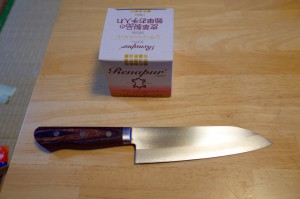以前感想を書いたことがある作品です。名前のごとく大変背の高い女の子富士山さんと、幼なじみの比較的背が低めの上場くんがつきあい始めて云々という話で、少なくとも90年代後半にその年代だった私としては、「ああ懐かしい、あんな感じだったなぁ」という作品全体の感想。まぁ、当時自分には彼女なんていなかったんですが、「おつきあい」を取り巻く雰囲気がそんな感じだったなぁと。
やろうと思えば受験の後の高校時代だって続けられる作品ですので、いつまで続くのだろうなぁという感じだったのですが、この度8巻にて完結。8巻にて一大イベントが描かれるわけですけど、そこもまた、上手く落としたなぁという感じ。うんそれって重要だよね、と。至って健全ですから、ご安心?ください。
今回もう一件カップルが成立?しますが、その片割れである野球部で格好良く、女子に人気のある梅木くんが「付き合うってなにしたらいいんだっけ?」と言っているのに対して、上場くんは彼女がいて、付き合うってなにしたらいいのか知っている。上場くん、イマイチ女子に人気はないが、なかなか男気のある良い彼氏だっていうのを読者は延々イチャコラを見ているので知っている。……好対照で良いですね。不特定多数に人気があるかどうかというのは、特定の人の恋人として好適な人物なのかは別問題なのだなぁというのがよく分かります。
付き合っているのを同級生に知られるのすら恥ずかしかった、懐かしのあの頃を思い出す。思春期マンガの白眉です。